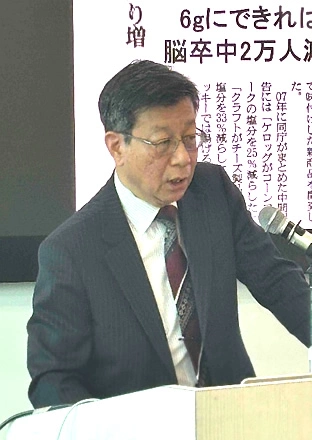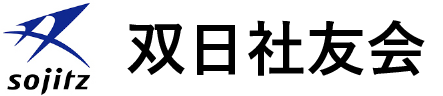【東京本部】講演会報告「健康長寿のまちづくり」
| テーマ | 「健康長寿のまちづくり」 |
|---|---|
| 講師 | 千葉大学特任教授 近藤克則氏 |
2月9日(木)双日本社21階会議室において、東京本部の講演会を開催しました。講師は、介護予防の観点から高齢者ケアの在り方、健康長寿の町づくりなどを研究されている千葉大学特任教授近藤克則様です。以下講演内容の一部をご紹介します。
健康長寿の割合は市町村に差がある
認知症になりやすい町とそうでない町で4倍もの格差があります。日本老年学的評価研究(JAGES)が2010年から3年間の追跡調査で得られた24の市町村で、名古屋市を1とすると3を超える市町村が7つありました。幸福だと感じる人の割合についても差があり、少ない町だと3割、多い町だと6割いることがわかりました。30分以上歩く人が多い町で認知症になる人が少ないようです。従ってどうすれば歩く人が増えるだろうかという研究は世界中で行われています。かつて我が国でも健康の為に歩きましょうと大々的にキャンペーンを行いましたが成果は上がりませんでした。ただ歩きましょうと言っても人の行動は変わらないのです。
長寿健康な人の割合が市町村によって相当な差があります。その原因は何か、どういう要因が考えられるのかを、近藤教授は長期にわたる膨大な調査データをもとに解明に努めておられ、我々社友会世代にとって関心もあり、その説明は非常に説得力がありました。どうすれば人は歩くようになるのか。商業施設、公園、広い歩道、美しい街並みなどに加え、治安や交通機関の状況などとの関係もあり、そうした調査研究の結果を協力してくれた自治体とも共有することで町づくりに繋げていきます。
高齢者9万人を3年間追跡して、どのような社会活動が介護予防になるかの調査結果の説明もありました。一番効果があるのは就労でした。次がスポーツ、町内会活動、ボランティアへの参加なども効果が確認されています。社会と関わっていることがよさそうです。運動は定期的に、1人よりグループで参加のほうが介護予防の効果があります。食事、笑いもグループのほうがよいという結果になりました。孤食はダメです。これらを総合的にみると社会的繋がりが大事で、社友会の活動に参加するのもよいことと言えます。予防医学の考え方は、病気の原因を解明してその情報を伝えるだけはなく、原因の原因にさかのぼって、その原因の原因に介入して行動を変えて健康にしようという考え方です。だから健康なまちづくり、社会づくりをするということになります。
介護予防の全国的取り組み
イギリス発祥の社会的処方箋という考え方が日本に伝わり、骨太の方針の政策のひとつとして閣議決定され、日本でも実施することになりました。モデル事業が終わり、これから本格的事業に入るところです。住民主体の活動で自分たちが楽しいと自覚すると介護予防効果があります。こうした活動を厚生労働省が全国に広げ、今では、全国の1700市町村の95%が取り組んでいます。ご興味のある方は市役所、地域包括支援センターに問い合わせてみてください。ご自分の住む地域でどのような活動があるかが分かります。
こうした活動を全国で展開することで、マーケットが広がり、産業界でも関心が高まってきました。厚生労働省と経済産業省の連名で、成果連動型民間委託契約方式(医療・健康及び介護分野の手引き、令和6年3月)という契約形態が生まれました。Pay for Success、つまり成功したら報酬を増額するという考え方です。厚労省の調査によると、日本の高齢者は約3600万人で、平成27年から令和5年にかけて要介護の方が17.9%から16.3%まで1.6%減っています。一人当たり介護サービスに使っている金額は年間200万円ですから3600万人の1.6%で約60万人とすると、合計1兆円規模の介護給付費節約の可能性が見え始めています。
高齢者は認知症にならずhappy、子世代は介護離職せずにhappy、保健所は介護給付費が減ってhappy、それが波及すれば保険料も安くなるので、全高齢者happyで、誰も損をしないすごい仕組みとなります。全国でモデル事業をやっています。現在立ち上がりのフェーズです。私たちが関わったところでは岡山市、堺市、豊田市などがあります。
本日ご参加の方へ
総合商社は新しいビジネスモデルを世界中で創ってきたと聞いています。自治体が抱える社会課題を、地域の企業やボランティア団体をマッチングさせて新しいビジネスモデルと作る人を求めています。商社パーソンは最適です。そういう人たちが集う場所、プラットフォームを作ろうというので、安寧社会共創イニシアティブ(An-nei Community Co-Creation Initiative「AnCo(あんこ)」(URL:https://annei.org/)を昨年秋に立ち上げました。問題意識を共有する京都大学、千葉大学とか自治体とか、民間企業に声をかけて、現在会員募集中です。個人会員もありますので、是非加入して頂きたいと考えています。いろんな分科会でチームをしぼり、いろんなとことでマッチングをして、そういうモデルを日本中に増やしていきたいと考えています。皆さんの認知症予防にも役立ちます。皆さんのご協力をお願いしたいと存じます。
(報告者:高橋哲夫)